特定技能外国人のキャリアアップに関する情報交換会
2025年1月16日(木)、飲食料品製造業分野・外食業分野における特定技能外国人のキャリアアップをテーマに、情報交換会が開かれました。「1号特定技能外国人の育成」と「特定技能2号の活用」にスポットを当て、受入事業者、外国人材、登録支援機関、関連事業者、自治体の担当者など約20名が参加し、課題や実践例を共有しました。

- 会期
- 2025年1月16日(木) 14:00~16:00
- 場所
- 株式会社JTB ビジネスソリューション事業本部第二事業部内 会議室
- 主旨
- 特定技能外国人( 1号および2号)の育成・キャリアアップに関する各担当者からの 「課題感の洗い出し」
- 対象者
- 特定技能外国人受入事業者、特定技能外国人、登録支援機関、関連団体、自治体、農林水産省
- 人数
- 約20名(受入れ事業者4社、特定技能外国人3名、登録支援機関2社、外国人材関連事業者1社、関連団体1社、自治体4団体、農林水産省)
- 受入れ事業者属性
- 飲食料品製造業分野受入事業者/和菓子製造業、中華料理専門店(セントラルキッチン事業)
外食業分野受入事業者/中華料理専門店経営、居酒屋経営
1号特定技能外国人の育成
日本語能力の向上
特定技能2号の飲食料品製造業分野及び外食業分野への拡大に伴い、受入事業者には特定技能外国人の長期的なキャリア形成をサポートすることがより求められるようになりました。しかし、技能や日本語能力の向上、外国人材のキャリアアップに対応する職場づくりなどについては、現場レベルでさまざまな課題があります。特に日本語能力はキャリアアップにおいて土台になるものですが、受入事業者や登録支援機関から、
- ・「例えば、同じ日本語能力試験N3合格者でも、読み書きはできるが会話が苦手だったり、逆に会話はスムーズだが読み書きに難があったり、個人差が大きい」
- ・「業務を覚えるのに精一杯で日本語学習がなかなか進まない。技能の育成と日本語能力の育成をどう並行して進めていくかが課題」
- ・「日本語学習の授業をオンラインで提供しているが継続率が低い」
といった問題意識が共有されました。
日本語能力を高めるため、各事業者や自治体もさまざまな取組を実践しており、
- ・「読み書きが苦手な方には日報を毎日書いてもらい、指導している企業がある」
- ・「日本語能力試験の2か月前から毎週1回、能力別クラスで日本語教室を実施している」
- ・「多国籍の参加者が集まるイベントを開き、楽しく日本語でコミュニケーションする時間を設けた」
- ・「評価面談とは別に、外国人材と担当社員が1対1で“雑談”する時間を設けた。業務以外でも日本語で話す機会ができ、日本語学習の意欲や進捗も確認できる」
- ・「日本語学習は最終的には個人の努力次第。ラジオなどで耳を慣らすことからスタートすると効果的では」
- ・「日本語レベルや性格がそれぞれ違うので、個人に合わせたコミュニケーションを取っている」
など、さまざまな実践例が紹介されました。
学びのモチベーションを高めるには
一方で、日本語学習のモチベーションにはどうしても個人差があり、意欲の低い人にどう働きかけていくかが課題です。ある登録支援機関は「全員をレベルアップさせている受入事業者は、最優先でキャリアプランをしっかり策定している」とポイントを挙げた上で、
- ・「受入れ当初から『特定技能2号の取得を目指すなら日本語能力試験N3以上が必要』と伝える」
- ・「勉強会の参加率が高い人から特定技能2号技能測定試験を受けてもらう」
- ・「レベルに応じて資格手当を支給する」
といったキャリアプランと連動させた動機づけが効果的ではないか、と紹介しました。
また、外国人材からは、
- ・「日本語を勉強する仲間を見つけることが大切。さらに、会話練習だけでなく、同僚と仲良くなったり会社のイベントに参加したりして日本の文化や人々を理解することが重要だ」
- ・「2号特定技能外国人になることや収入アップがさらなる日本語学習のモチベーション向上に繋がる」
と、自らの経験を踏まえた意見が出されました。
日本人スタッフへの働きかけ
さらに、言葉の問題は外国人材に対する取組だけでなく「日本人スタッフの認識も重要」という指摘もあり、
- ・「日本人向けに、いかに自分たちが普段あいまいで分かりづらい表現、暗黙の了解、裏を読む必要がある表現を使っているかを気付かせる研修をした」
- ・「日本人スタッフから『注意しているのに笑ってごまかそうとするので困っている』と相談されたが、外国人材の中には、相手が怒っていても笑顔で接するのが誠意ある対応だという認識を持っている人もいる。そうした誤解を解消するため、日本人への働きかけも大切」
など、言語を含めた文化の違いを日本人側も理解することが、現場でのコミュニケーションの円滑化に繋がるのではないかという提案もなされました。
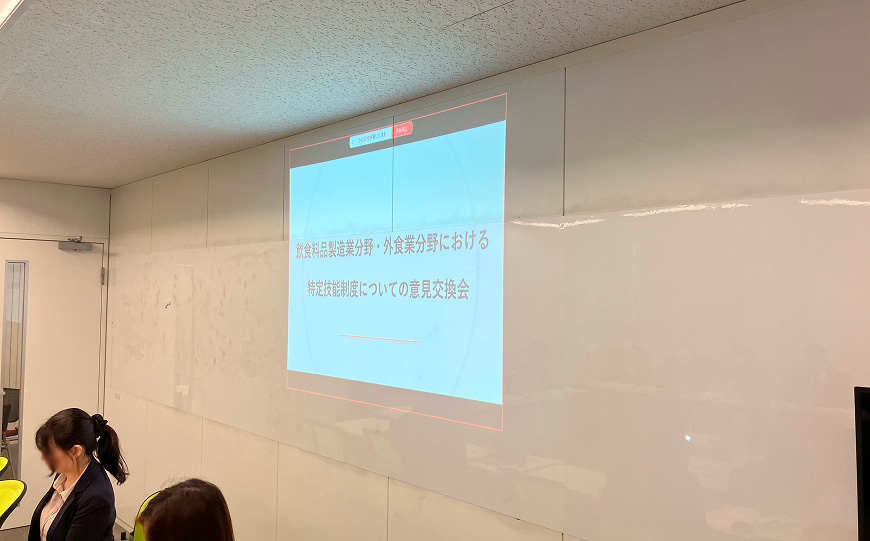
特定技能2号の活用
管理業務の定義付け
2号特定技能外国人へのステップアップでは、管理業務経験の要件が大きな課題となっています。受入事業者や関連事業者からは、「管理職」「役職」の定義や解釈の難しさ、実務との乖離について、さまざまな声が上がりました。
- ・「管理業務として具体的にどんな業務内容を書けばいいのか分かりにくい。書類が一度で受理されず、何度か提出し直した」
- ・「特定技能制度開始当初は、特定技能2号を想定していなかったため、ちょうど5年のタイミングで急に『2年以上の管理業務の実務経験を証明して』と言われても戸惑う事業者は多い」
- ・「日本人のベテランスタッフに役職がないのに、特定技能外国人を役職に就けるのは難しい。日本人スタッフとの処遇のバランスをどう取ればいいのか」
- ・「ほかの分野の例だが、受入事業者が業務に関する資格や免許の取得を奨励し、それをスキルアップと実務経験の裏付けとして活用している」
管理業務をどのレベルで、どの範囲まで担当すれば実務経験の条件を満たせるのか、多くの事業者が手探りの状態にあります。これに対し、農林水産省の担当者は、『管理職や役職の要件は、過度に高いレベルを求めるものではない』とし、基準をより明確にし、手続において誤解を生まない方向で改善することが示されました。
特定技能2号の技能測定試験対策
さらに、特定技能2号の取得においては、技能測定試験の難しさも課題として挙げられました。実際に受験して合格した方からは、
- ・「漢字が読めず答えられないことがある。簡単な日本語を問題に使うか、ふりがなを振ってほしい」
- ・「インターネットで調べても意味が分からない言葉が出てきて、勉強しにくかった」
と率直な意見が寄せられ、受入事業者からも「自分が見ても難しい」「知らない単語があり、外国人材と一緒に調べて勉強した」という声も上がりました。
各事業者では試験の対策として、
- ・「問題を実際の本人の業務に落とし込んで説明した」
- ・「試験前に補習授業を行った」
- ・「勉強用のテキストに社員がポイントを書き加えて共有した」
- ・「社内で練習問題を作って一緒に解いた」
など、それぞれが工夫を凝らしてサポートしていることが紹介されました。
帯同する家族へのサポート
外国人材が特定技能2号を目指すモチベーションの一つに、家族の帯同が挙げられます。
帯同した家族をケアする体制について、
- ・「家族は特定技能2号取得の動機づけとしてとても重要だ。ただ、家族まで受入事業者がフォローするのはあまりにも負担が大きい。これまで以上に自治体のサポートが必要で、それがなければ特定技能2号の活用は進まないのではないか」
- ・「今後、子や配偶者への日本語教育、生活や住居の支援は必要だが、多様な国籍や言語にいかに対応するかが課題」
といった現状や課題が共有されました。
まとめ
さまざまな課題や事例を踏まえ、農林水産省の担当者が「制度と実態のギャップを知る良い機会になった。制度の発展には、多様な関係者を巻き込みながら進めていく必要があるとあらためて実感した」「課題を共有していただき、我々も考慮すべきことが数多く見えたように思う。海外との人材獲得競争も激しくなる中、日本を選んでもらえるような制度設計を進めていきたい。特定技能制度が持続可能な制度となるようこれからもご協力いただきたい」とまとめ、継続的な改善と国、自治体、事業者などが一体となって取り組む必要性を確認し、会を閉じました。